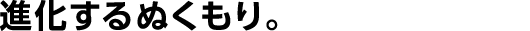JPPFCの歴史
1955年(昭和30年)
日本郵便友の会協会の設立
 8月16日には、郵便友の会の指導・育成団体として、「財団法人日本郵便友の会協会」(以下「協会」という)が発足しました。会長には、渋沢敬三国際電信電話株式会社社長、理事長に、関正雄全国郵便友の会連合事務局長が就任されました。
8月16日には、郵便友の会の指導・育成団体として、「財団法人日本郵便友の会協会」(以下「協会」という)が発足しました。会長には、渋沢敬三国際電信電話株式会社社長、理事長に、関正雄全国郵便友の会連合事務局長が就任されました。
1956年(昭和31年)
沖縄の高校生の本土招待と沖縄派遣
 3月23日から4月4日まで、近畿地連と協会近畿地方支部(昭和36年から本部に)は、古(現・使用済み)切手回収による収益金により、初めて沖縄の高校生4名を招待し、各地の郵便友の会会員との交歓を行いました。
3月23日から4月4日まで、近畿地連と協会近畿地方支部(昭和36年から本部に)は、古(現・使用済み)切手回収による収益金により、初めて沖縄の高校生4名を招待し、各地の郵便友の会会員との交歓を行いました。
また、1959年(昭和34年)からは、郵便友の会結成10周年を記念して本土の会員代表を送る「沖縄訪問親善使節派遣」を行うようになり、この行事は沖縄の本土復帰の年の1972年(昭和47年)までの13回に及びました。
在ソ同胞慰問運動
 全国連合では、5月11日付「ニュース」に在ソ抑留同胞リストを掲載。ソ連抑留同胞を慰問するため、激励の手紙や慰問品を送ったり、海外のペンフレンドには一日も早く帰国が実現するように協力を求めるように全国の会員へ呼びかけました。
全国連合では、5月11日付「ニュース」に在ソ抑留同胞リストを掲載。ソ連抑留同胞を慰問するため、激励の手紙や慰問品を送ったり、海外のペンフレンドには一日も早く帰国が実現するように協力を求めるように全国の会員へ呼びかけました。
また、留守家族の声の録音通信や留守家族の慰問を行う等の活動も展開されました。
基本規約の制定と世界青少年へ平和メッセージ
 8月4日から6日まで、仙台市と蔵王山青根で第8回全国大会が開かれ、「郵便友の会基本規約」制定と「全国郵便友の会連合規約」の一部改正について協議され、可決されました。
8月4日から6日まで、仙台市と蔵王山青根で第8回全国大会が開かれ、「郵便友の会基本規約」制定と「全国郵便友の会連合規約」の一部改正について協議され、可決されました。
また、全国委員長が「文通によってお互いに堅く手を結び合い、世界平和を打ち立てよう」と世界の青少年に向けてメッセージを朗読し、全世界の平和が実現するように訴えました。
イタリア支部の代表来日
 11月11日から一か月間、協会では、郵便友の会の普及と文通あっせんに努力している郵便友の会イタリア支部の代表ルチアナ・ガブリエリさんを招待し、東北・関東・関西の会員と交歓しました。
11月11日から一か月間、協会では、郵便友の会の普及と文通あっせんに努力している郵便友の会イタリア支部の代表ルチアナ・ガブリエリさんを招待し、東北・関東・関西の会員と交歓しました。
ガブリエリさんは、その後も数回日本を訪れ、全国各地の会員たちと交流を深めました。
世界を花で結ぶ運動
 近畿地連では、海外のペンフレンドあてに、日本特有の花の種子を送り、かわりに外国からも種子を送ってもらい、それを公園や施設の庭にまいて、世界中を花の輪でつなぐ「世界を花で結ぶ運動」を実施しました。
近畿地連では、海外のペンフレンドあてに、日本特有の花の種子を送り、かわりに外国からも種子を送ってもらい、それを公園や施設の庭にまいて、世界中を花の輪でつなぐ「世界を花で結ぶ運動」を実施しました。
日本からは、日本郵便友の会のシンボルである“なでしこの種”がよく送られました。この運動はその後もずっと続けられ、1960年(昭和35年)ごろから実施された「花いっぱい運動」へとつながっていきました。
1957年(昭和32年)
原水爆禁止運動
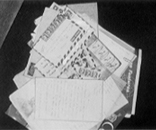 8月4日から6日まで、金沢市と永平寺で第9回全国大会が開かれ、大会式典の中で全国委員長が全世界の青少年に呼びかける原水爆禁止を訴えるアピールを読み上げました。このアピールは直ちに全国連合の名で、世界の主な国々の青少年団体や原水爆保有国、国連等へ送られました。また、この運動を推進するため、文通による海外ペンフレンドへの訴えや署名アピール、外国の知名人や新聞社等へ訴える活動が展開されました。
8月4日から6日まで、金沢市と永平寺で第9回全国大会が開かれ、大会式典の中で全国委員長が全世界の青少年に呼びかける原水爆禁止を訴えるアピールを読み上げました。このアピールは直ちに全国連合の名で、世界の主な国々の青少年団体や原水爆保有国、国連等へ送られました。また、この運動を推進するため、文通による海外ペンフレンドへの訴えや署名アピール、外国の知名人や新聞社等へ訴える活動が展開されました。
沖縄の霊石を贈る運動
 第9回全国大会より、毎年の大会へ参加出来るようになった沖縄の会員たちは、激しい戦いのあった土地の石を集め、遺骨のかわりに本土の遺族へ贈ろうという活動を、11月から始めました。
第9回全国大会より、毎年の大会へ参加出来るようになった沖縄の会員たちは、激しい戦いのあった土地の石を集め、遺骨のかわりに本土の遺族へ贈ろうという活動を、11月から始めました。
沖縄の会員は日曜日ごとに南部最大の激戦地であった麻文仁(まぶに)へ出掛けて石を集め、その石は7万個に及び、各地のPFCを通じて、遺族の手に渡されました。
1958年(昭和33年)
特別会員グループ全国協議会の発足
 8月5日から7日まで、松山市と高松市で開催された第10回全国大会と平行して、郵便友の会の青年部である特別会員の「特別会員連絡協議会」が開催されました。
8月5日から7日まで、松山市と高松市で開催された第10回全国大会と平行して、郵便友の会の青年部である特別会員の「特別会員連絡協議会」が開催されました。
その協議の中で全国組織の結成について話し合われ、特別会員グループと特別会員の全国組織として、「郵便友の会特別会員グループ全国協議会」が発足しました。
フィオセスへの加盟
 8月、協会は各国の加盟団体との情報交換および会員に対するペンフレンド紹介サービス向上を図るため、国際学生文通交換機構連盟(Federation Internationale des Organisations de Correspondances et d'Echanges Scolaires 略称FIOCES=フィオセス)へ加盟しました(日本では唯一の加盟団体です)。
8月、協会は各国の加盟団体との情報交換および会員に対するペンフレンド紹介サービス向上を図るため、国際学生文通交換機構連盟(Federation Internationale des Organisations de Correspondances et d'Echanges Scolaires 略称FIOCES=フィオセス)へ加盟しました(日本では唯一の加盟団体です)。
1959年(昭和34年)
オリンピックシールによる東京オリンピック招致運動
 1月から、1964(昭和39年)のオリンピックが東京で開催されることを希望する意思を表す意味で、オリンピックマーク入りのシールを手紙にはりつけ、国際オリンピック委員会(IOC)や海外のペンフレンドあてに招致を促す運動を実施しました。
1月から、1964(昭和39年)のオリンピックが東京で開催されることを希望する意思を表す意味で、オリンピックマーク入りのシールを手紙にはりつけ、国際オリンピック委員会(IOC)や海外のペンフレンドあてに招致を促す運動を実施しました。
また、オリンピック資金財団の要請を受け、オリンピックシールによる東京オリンピック開催資金作りに協力するため、「オリンピックシール10円募金活動」を行いました。
海外日本移民へ本を送る運動
 ブラジル日本移民50周年をきっかけに、同国の日系人との文通が激増しました。会員は受け取る手紙の中で、本の不足を知らされ、「海外移民に本を送る運動」を郵便友の会結成10周年記念行事として、郵政省や外務省等の後援を得て実施しました。
ブラジル日本移民50周年をきっかけに、同国の日系人との文通が激増しました。会員は受け取る手紙の中で、本の不足を知らされ、「海外移民に本を送る運動」を郵便友の会結成10周年記念行事として、郵政省や外務省等の後援を得て実施しました。
6ヶ月間に、4万6千冊(単行本、教科書、マンガ、絵本、週刊誌、月刊誌)が全国から届き、ブラジルやパラグアイ、ドミニカ、ボリビアの中南米各国の日本移民の人々へ送られました。
1960年(昭和35年)
誤解されている日本の是正運動
 1月23日に開催された東京都連常任委員会で、外務省の外郭団体が集めた外国の教科書で紹介されている日本の姿が江戸時代や戦前のものであったり、中国の風俗と混同されている等、時代錯誤や事実の誤解の例が多数あることが確認されました。
1月23日に開催された東京都連常任委員会で、外務省の外郭団体が集めた外国の教科書で紹介されている日本の姿が江戸時代や戦前のものであったり、中国の風俗と混同されている等、時代錯誤や事実の誤解の例が多数あることが確認されました。
そこで、東京都連が立ち上がり、外国のペンフレンドに向けて、日本の今日の姿を伝える写真や雑誌、本等を積極的に送り、少しでも正しい日本の姿を世界の人々へ紹介していこうと「誤解されている日本の是正運動」の実施が決議され、全国へと運動の輪が広がっていきました。
千葉県に初の顧問組織発足
 8月4日から6日まで、熊本市等で開催された第12回全国大会中に、「顧問教官(現・顧問教師)研究協議会」が開かれ、郵便友の会と学校教育活動との結び付き等が協議されました。
8月4日から6日まで、熊本市等で開催された第12回全国大会中に、「顧問教官(現・顧問教師)研究協議会」が開かれ、郵便友の会と学校教育活動との結び付き等が協議されました。
その結果、10月22日、全国初の顧問教官組織として、「千葉県郵便友の会連合研究会(現・千葉県文通教育研究協議会)」が発足しました。
1962年(昭和37年)
文通で結ぶ若い友情運動
 5月から11月まで、集団文通の推進と文集作り、組織の拡充を図ろうと「文通で結ぶ若い友情運動」が展開されました。
5月から11月まで、集団文通の推進と文集作り、組織の拡充を図ろうと「文通で結ぶ若い友情運動」が展開されました。
文通によって遠く離れた地方、環境の異なる地域に住んでいる青少年たちがお互いに同世代者としての結び付きを確かめ合い、励まし合おうと、グループ間の文通運動が行われました。
1963年(昭和38年)
全国文通教育研究協議会の発足
 千葉県の顧問組織の発足をきっかけに全国各地に顧問教師の組織が誕生していきました。
千葉県の顧問組織の発足をきっかけに全国各地に顧問教師の組織が誕生していきました。
前年、広島市の宮島で開催された第14回全国大会にあわせて、第8回顧問教官研究協議会が開かれ、「全国郵便友の会文通教育研究協議会(現・全国文通研究協議会)」の設立が決議され、発足しました。
そして、この年の8月7日から9日まで、長野で開催された第15回全国大会で、発会式と新組織としての第1回の研究協議会が開催されました。
1964年(昭和39年)
目の不自由な人に録音テープを送る運動
 4月21日付「ニュース」で、目の不自由な人の生活に潤いを与えるため、学校の生活やクラブ活動の様子、町の話題、名所案内等を録音テープに吹き込んで送る「目の不自由な人に録音テープを送る運動」を呼びかけました。
4月21日付「ニュース」で、目の不自由な人の生活に潤いを与えるため、学校の生活やクラブ活動の様子、町の話題、名所案内等を録音テープに吹き込んで送る「目の不自由な人に録音テープを送る運動」を呼びかけました。
「声のたより差し出し運動」とも呼ばれ、石川県金沢女子短期大高校(現・金沢学院大附属金沢東高校)グループが吹き込んだテープを点字図書館へ寄贈したのをはじめ、目の不自由な人々へ送られました。
ネパールの結核を救うための古切手運動
 このころから、ネパールの結核を救うために古切手を集めてお金を作り、予防ワクチン(BCG)を送ろうとの呼びかけが頻繁に行われました。
このころから、ネパールの結核を救うために古切手を集めてお金を作り、予防ワクチン(BCG)を送ろうとの呼びかけが頻繁に行われました。
これは1967年(昭和42年)ごろまで全国各地で行われ、協会がその集積の労にあたりました。